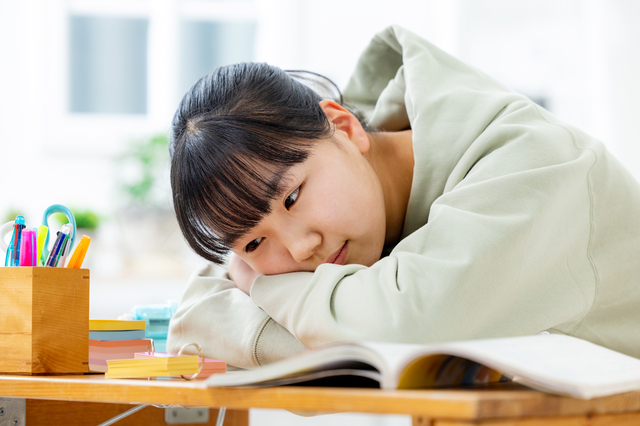
中学生になると不登校が増える?その理由は?親子それぞれの対処法もご紹介!
それにより起こる問題の1つとして「不登校」が挙げられます。
実際、中学になってから不登校者数は激増すると言われており、 近年情報では小学校の不登校者数は約6万人と言われているのに対し、同年の中学の不登校者は約13万人だったいうデータもあります。
そこで今回は、不登校が増える理由として考えられる要因から、親と子の対処法までまとめましたのでご紹介したいと思います。
途中、「学校に行きたくないと言われたらどうするかについてもご紹介してますので、 是非最後までご覧ください。
● 中学生になると不登校になる子が増えるのはなぜか
● 「学校に行きたくない」といわれたらどうするか
● 子どものケアと同時に親もケアが必要
1. 中学生になると不登校になる子が増えるのはなぜ?
これらは小学校とは違い、中学生に近付くと誰にでも起こり得そうな案件だと予想できますが、なぜ、それらが不登校に繋がってしまうのでしょうか?
1-1. 人間関係が大きく変化するから

不登校の原因で第一に上げられるのが人間関係の変化が一因と考えられます。
小学校はみんなで仲良くしましょう、という傾向がありますが、
中学生という年頃になると、服や趣味のセンスなど共通点の有無で友達を選ぶ傾向になりやすいです。
その結果、自然とグループで付き合うようになり、その人間関係に溶け込める人、溶け込めない人が出てきます。
また、先輩・後輩など小学校にはない関係が増える事で、戸惑いが増えます。
また、小学校まではクラスごとの担任制度だったのが、中学になると教科担任制に変わるため、誰に相談したら良いか分からないという子どもも出てきます。
その結果、不登校に追い込まれるパターンが考えられます。
1-2. 思春期で親子の関係性が変わる

思春期を迎え体と心の発達が進んでいくと、子ども自身も大人に近づいているという自覚が出てきます。
それと同時に、親のほうも「自分でやりなさい」と、子どもに自立を促す傾向になりがちです。
その結果、お互いに「もう思春期だから」「もう子どもじゃないから」という意識が生まれ、 親子の関係性が変わる原因に繋がっていくと考えれます。
子どももいつまでも幼児ではありませんので、思春期は親子の付き合い方を変えてあげるタイミングとも言えますが、
自立の意識が芽生えた結果「親に相談するのは恥ずかしいこと」
と考えてしまう子どもも少なくありません。
その結果、精神的に孤独を感じやすくなってしまい、それが不登校という形となって現れるパターンもあります。
2. 「学校に行きたくない」と言われたらどうする?
ベストな方法は子どもの言い分や状況によってさまざまですが、絶対にこれだけはやるべき共通ポイントを三つ紹介します。
2-1. まずは子どもの気持ちに寄り添って

必須なのは、まず子どもの気持ちに寄り添う事です。
話を聞き、肯定してあげる事で、子どもは「自分の気持ちを受け止めてくれた」と感じます。
例え、子どもが話してくれなくても「うんうん。話してくれるまで待つよ。」「あなたの味方だよ。」と子どもの気持ちに寄り添う姿勢を見せ続けることで、子どもも徐々に安心感を得られ、傷ついた心をケアする事につながります。
2-2. 必要に応じて学校に相談

不登校の要因が、学校生活の中にあるようなら、学校に相談してみるのも良いでしょう。
学校は教育機関でもありますので不登校の対応に長年対処してきた教師も在籍していると考えられますし、家庭とはまた違った、適切な対処法を教えてくれる事に期待できます。
学校によっては、保健室や図書室の別室登校など、別の形での登校スタイルをもうけている所もあります。
スクールカウンセラーが在籍してるなら、第三者の手を借りるのも良いでしょう。
ただ、自分の心情を、学校の人に知られたくないと考える子どもの場合は、そこは慎重に進めていかないといけません。
2-3. 家庭学習を検討する

学習能力の延滞を防ぐため、自習・家庭教師・通信制のフリースクールなど、学校以外の学習も検討してみるのも1つの方法です。
学校に行かなくなったことで、平日日中のルーティンが失われ、生活習慣が乱れがちになってしまう問題も出てきます。
家庭学習を取り入れるのは、それを防ぐための1つの方法と言えます。
学力をキープしておくと、本人が復帰する気になった時に、学校に復帰しやすくする対策にもなります。
学校に復帰する意思が今のところ見られない子どもの場合でも、学校に行く以外の選択肢を与える事で、子どもが精神的に楽になることが期待できます。
3. 子どものケアと同時に、親もケアが必要
親子カウンセリングもその一環ですが、 なぜ不登校になった本人だけでなく、親もケアが必要なのでしょうか?
3-1. 両親の心の安定が子どもの安心感につながる

子どもの不登校問題を抱えている事で、本人だけでなく、親も子どもの将来の不安や、焦りなど、心理的不安を抱えます。
表面上は、穏やかにしていても、それを子どもの前で24時間キープしておくのは難しいですよね。
親の不安定な様子を見せてしまうと、「自分のせいで親を悩ませてしまった」と子どもが自責の念に駆られたり、親子で不安定になってしまい共倒れになる可能性も出てきます。
それらを防ぐために、親も何らかの対処法を見つけ、心を安定させておく必要があります。
子どもの不登校問題は親がしっかりと軸を持ち、接することが理想と言えます。
親子カウンセリングや、可能であれば子どもをよく知る親族など、第三者の手を借りるなど、心を安定させる方法を見つけましょう。
3-2. 悩みを抱え込まず、リフレッシュしよう

自分と子どもを追い詰めないためにも、まず、抱え込まないことが大切です。
いったん、不登校問題から離れて、違うことを行ってみるのも良いでしょう。
例をあげるなら、親子で料理やスポーツをしてみたり、部屋を模様替えして、いつもと違う雰囲気にしてみるのもリフレッシュになるでしょう。
遠出してみたり、旅行などで、一時的に環境を変え、学校と家から離れてみるのも良いとされています。
もちろん、子どものケアも大切ですが、いったん悩みを抱えるのを放棄する時間を作るのもよいでしょう。
4. まとめ

以上不登校問題についてまとめてみました!
まとめると以下の通りです。
● 中学生になると不登校になる子が増える、最もな要因は人間関係と思春期である
● 「学校に行きたくない」といわれたらまず、本人の気持ちに寄り添い、学校に相談
● 家庭での学習を検討する事も選択に入れるのもあり
● 子どものケアと同時に親もケアが必要。心の安定が子どもの安定と言える
● リフレッシュも大切
との事でした。
中学生の不登校問題。
小学校とは違う悩みも増えてくるため、どう導いてあげたら良いか、戸惑う問題かと思います。
しかし、これらの記事を読んで頂き、
自分達は何をすべきか・自分の子どもが抱える問題はどこにあるのかが
見えるヒントになれば、
改善への一歩に繋がるのではないでしょうか?
これらの情報が参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
