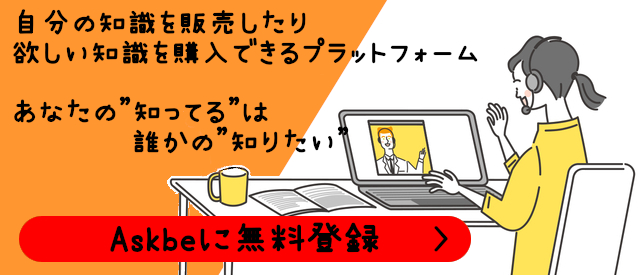早期教育は何歳から?ひらがなが読めるようになる平均年齢と子どもが興味を持つ学習方法をご紹介
いつから勉強させたらいいのかと気になる方もいるのではないでしょうか。
また、すでに勉強を始めさせているが子供が全く興味を示さない、ひらがなを覚えられないと不安に感じている方もいるかもしれません。
今回はそんなお悩みを解決できるように
● 小学校入学前にひらがなの読み書きができるのはどれくらいなのか
● ひらがなへの興味を持たせるには、興味を持たない場合はどうしたらよいのか
のお悩みについて書いています!
1. 小学校入学前にひらがなの読み書きができる子はどれくらい?

まずひらがなの読み書きができるようになるのは何歳が多いのか見ていきます。
ひらがなの読み書きは早い子だと2歳からできるようになり、8割以上の子が4歳ごろには読めるようになります。
また、自宅などで早期教育を始める年齢は3歳からが14%、4歳からが26%、5歳からが32%で約7割の家庭が小学校入学前に早期教育を行っています。
これだけを聞くと読み書きをまだ始めていないお子さんがいるご家庭は焦ってしまうかもしれません。
ですが、小学校入学前に読み書きができなくても問題ありません。
2. 入学前に読み書きができなくても大丈夫?
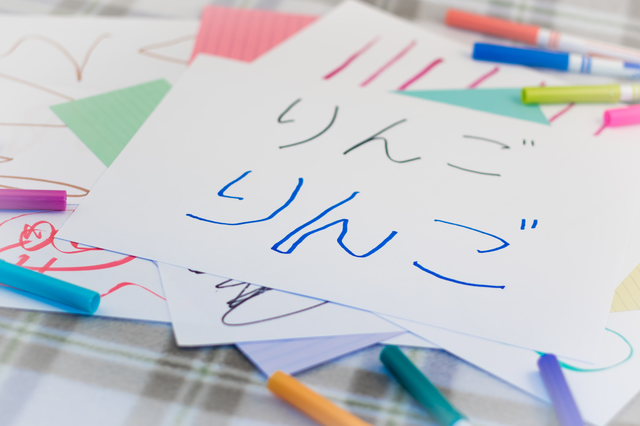
ひらがなの読み書きに興味を示すには個人差があります。
そのため無理やりに教えることで苦手意識が出てきて勉強が苦手になったり、ひらがなの読み書き以外の学習も嫌いになってしまうことがあります。
そのため、無理やりに勉強させるのではなく読み聞かせを習慣化したり、遊びや好きなものの中でひらがなに触れる機会をつくるなど子どもが興味を持つようにすることが大切です。
小学校入学前に読み書きができなくてもほぼ問題はありません。
小学校に入学してから読み書きを覚えることで正しい書き順を学ぶことができます。
また、学校で学んだ文字が宿題として出されるので、すぐに復習ができ文字の習得も早くなります。
小学校入学前にひらがなを書けるようになっていた場合でも、文字自体を間違っていたり、書き順を誤って覚えてしまっている場合もあります。
一度間違えたまま覚えてしまうと正しく覚えなおすのに時間がかかるため、最初から小学校で学ぶほうがいい場合もあります。
小学校入学前は自分の名前がひらがなで読めるだけで十分です。
小学校入学前にひらがなの読み書きはできなくても大丈夫とお伝えしてきましたが、それでも心配になる方もいるでしょう。
では、どのようにして子供に文字に興味を持たせたらよいか、早期教育ではどのようなことをするのがおすすめかを見ていきます。
3. 子どもに興味を持たせるには

子どもは「聞く→話す→読む→書く」の順番で言葉を学習します。
ひらがなに興味を持ち学習するまでには以下の流れがあります。
①大人が話しかけることで言葉の存在を知る
②伝えたい気持ちがあるときに聞いた言葉を使って自分で話す
③「話し言葉」と「書き言葉」があることを知り、ひらがなを読むようになる
④書くことで気持ちを伝えたいと思うようになりひらがなを書くようになる
そのため小さいころから話しかけることで「聞く、話す」ことへの興味を刺激することができ、早い段階から「読む、書く」ことへの興味を示すようになります。
ひらがなに興味を持たせたい場合は無理やり読み書きをさせるのではなく、子供が理解している、していないにかかわらず、小さいころから大人が積極的に話しかけ言葉に興味を持たせることが大切になります。
子どもにひらがなを無理やり覚えさせようとしても、子ども自身に興味がなければ覚えることはできません。
子どもは遊びや周囲とのかかわりを通じてひらがなに興味を持つため、「興味」と「体験」が大切です。
子どもに話しかける以外にも、絵本の読み聞かせや手遊びなども有効です。
絵本の読み聞かせは言葉の数を増やす力があります。
いろいろな言葉を聞くことで、文章から言葉の意味を知り、自分で言葉を使って会話をしようとします。
また、話ことばだけでなく書き言葉を学ぶきっかけにもなります。
図書館などでたくさんの本が借りられるので手軽に始めることができます。
手遊びは手遊び歌の中に様々な言葉が出てきます。
繰り返し歌い聞かせることで、自然と歌を覚え、言葉を覚えることができます。
また、親子のスキンシップやコミュニケ―ションもとることができるので一石二鳥といえます。
言葉をある程度覚えたらしりとりやかるたなども有効です。
しりとりは知らない言葉を覚えることができるので、語彙力アップを期待できます。
また、かるたは文字の認識ができるようになるのでおすすめです。
読み手も取り手もどちらもひらがなを読む力が身に付きます。
遊びながら学習していくことが、子どもが楽しみながら勉強するためには必要になります。
4. こんな場合は専門家に相談しよう

これまで小学校入学までにひらがなの読み書きができなくて大丈夫とお伝えしてきました。
それは多くの子どもが小学校の入学前にひらがなに興味を持ち始め、自然と読み書きはできるようになったり、小学校の学習の中でひらがなを学んでいくからです。
そのため、お子さんが小学校入学前に読み書きが全くできなくても、心配しすぎる必要はありません。
小学校入学前にひらがなの読み書きに興味を示さず、読み書きができなくても、小学校に入学すると夏休みまでに何度も練習するのでいつの間にか身についています。
しかし、なかには「読字障害」「書字障害」など発達障害の一種として文字を読んだり書いたりすることが極端に苦手な場合もあります。
「読字障害」とは
単語のまとまりから一つの単語を識別したり、一つの単語の中から構成要素を識別したりすることが困難な読みの障害のことです。「書字障害」とは
文字書くときにマスや行から大きくはみ出してしまう、鏡文字を書いてしまうなど書くことが困難な障害です。書字障害は読字障害に伴って引き起こされている場合もあります。読字障害、書字障害にはいくつかの特徴があります。
● 幼児期から全く文字に興味を示さない
● 一文字一文字拾うように読み上げる
● 話や文節の途中で区切ってしまう
● 黙読が苦手
● 文字を読むとすぐに疲れてしまう
● 「わ」と「は」、「お」と「を」の区別ができない
● 「め」と「ぬ」など形が似ている文字を間違えて書きやすい
上記は一例ですが、そのような「何か違う」と感じる症状がある場合は「読字障害」「書字障害」の可能性もあるので一度専門家に相談することをおすすめします。
5. まとめ
子どもが興味を持っていないのに無理やりに教えることで勉強嫌いになったり、正しくない書き順で文字を覚えてしまい、小学校入学後に覚えなおさないといけなくなることもあります。
小学校入学前には自分の名前をひらがなで読めれば十分です。
しかし、それでも親の気持ちとしては周囲と同じようなレベルまでは読み書きができるようになっていてほしいと思うでしょう。
子どもに無理に勉強させるのではなく、楽しく学習できるように読み聞かせやゲームの中で子どもがひらがなに興味を示していく環境づくりが大切です。
そうすることで子ども自身からひらがなを学ぼうとしたり、勉強への苦手意識がなく、自ら前向きに勉強する意欲を見せるようになるでしょう。
Askbe(アスクビー)でスマホやPCでレッスンを配信・受信しよう!
講師にも受講者にもなれるレッスン+動画教材販売プラットフォーム