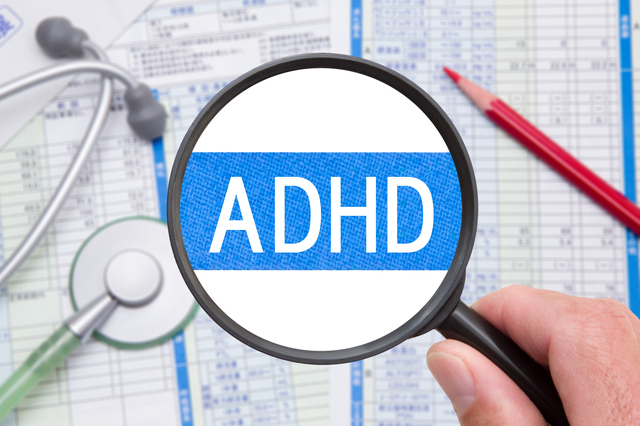
ADHDとは?ASDやLDの違いは?グレーゾーンとは?わかりやすく項目に分けて徹底解説
公開日: 2023/1/13
「発達障害」お子さんがそう判断されると、親としては悩まれるとともに鬼のようにネット検索してしまいますよね。
発達障害は検索すればするほど、診断の範囲が幅広く、あまりの情報の多さに 「結局、自閉症なの?特性なの?」と戸惑う方は多いのではないでしょうか?
今回は、発達障害の概要や、気を付ける点など 「詳しく調べたいが情報が多すぎる」「何の情報から良いか分からない」といった親御さんのために
●発達障害とその種類とは
●発達障害の「グレーゾーン」とは
●コミュニケーションで気をつけることとは
の3つに要点を絞りお伝えしたいと思います。是非最後までご覧下さい。
発達障害は検索すればするほど、診断の範囲が幅広く、あまりの情報の多さに 「結局、自閉症なの?特性なの?」と戸惑う方は多いのではないでしょうか?
今回は、発達障害の概要や、気を付ける点など 「詳しく調べたいが情報が多すぎる」「何の情報から良いか分からない」といった親御さんのために
●発達障害とその種類とは
●発達障害の「グレーゾーン」とは
●コミュニケーションで気をつけることとは
の3つに要点を絞りお伝えしたいと思います。是非最後までご覧下さい。
1. 発達障害とその種類とは
まず発達障害は3つに分類されています。
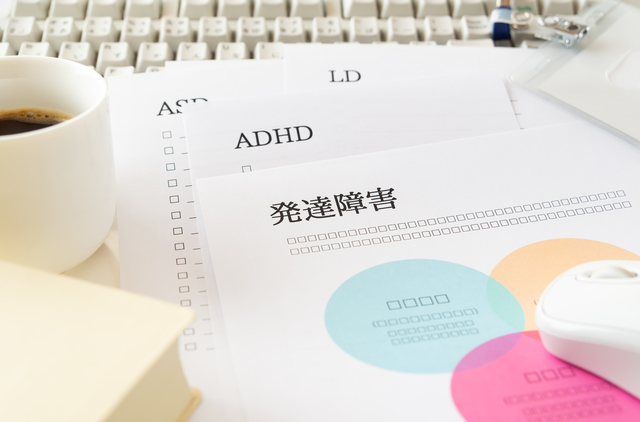
発達障害で検索すると、アスペルガー症候群・広汎性発達障害・自閉症というワードが出てくるかと思いますが、これらもすべてASDに含まれます。
ASDの原因は、現時点で詳しく解明されていませんが、生まれつきの脳の機能に原因があると言われています。
近年では20から50人に1人が自閉症スペクトラムと言われており、男性が割合的に多いと言われています。
具体的な症状は
●視線が合わない
●表情が乏しい
●偏食
●名前を呼んでも振り向かない
●パニック・睡眠障害
などがあります。
基本的に投薬などの治療はなく、本人の特徴・性質に合わせた療育・教育が主な対処方法になっています。
ただ、パニックや睡眠障害など本人の健康に弊害が出る場合は投薬を用いられる事があります。
「際立って手がかかる子」「手が付けられないくらい暴れる子」 と思われがちですが、けっして親のしつけ等が原因ではなく、行動・感情をコントロールする前頭葉の機能に原因があると言われています。
ADHDの種類は3つに分類されており
●不注意型(集中力不足・忘れ物が多い・他からの刺激ですぐに気を取られるなど)
●衝動・多動型(落ち着かない・感情のコントロールが苦手)
●混合型(不注意型・衝動多動型の両方を兼ねている)
があります。
ADHDは大人になると症状が落ち着いていくパターンもありますが、近年では「大人の発達障害(ADHD)」が話題になっており、大人になっても症状が続くパターンや、アルコールや薬物依存などを併発してしまうパターンもあります。
対処法は、本人の特性に合わせた環境調整(忘れ物等の対処はメモやチェックリストを活用する・本人の特性に付いて周囲に伝えておくなど)や、症状によっては投薬治療なども行われています。
それゆえ、本格的な学習生活に入る小学校に上がってから発覚するパターンも多く 原因は脳機能の障害と言われていますが、はっきりとは分かっていません。
LDの傾向は3つに分かれており
●読字障害・ディスレクシア(字の読み間違い・文字や文章が理解できない)
●書字表出障害・ディスグラシア(文字が正しく書けない・書き写しや文の作成に時間がかかる)
●算数障害ディスカリキュア(数の概念を理解しづらい・計算が困難)
があります。
これらの症状から「勉強が出来ない人」と捉えられがちですが、けして本人の努力不足などではありません。
対処法としては、字が拡大された教材を使用する・PCやスマホなど電子機器の読み上げ機能を使用する、イラストを使用して数の概念を理解させる、など学習方法や教材の工夫、周囲の理解が必要不可欠になります。
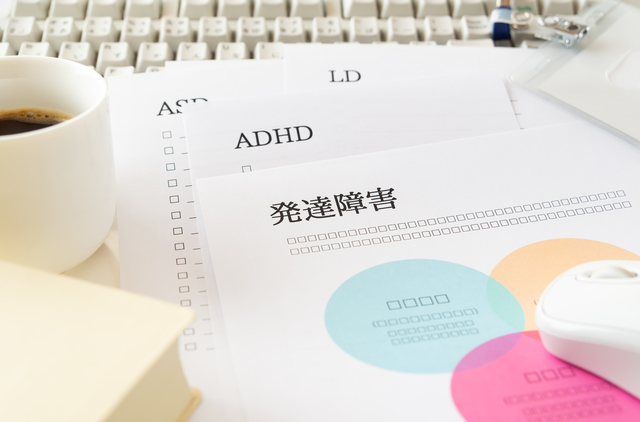
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症とは、コミュニケーションの取りづらさや、興味のかたより・こだわりが極度に強いことが代表的に挙げられます。発達障害で検索すると、アスペルガー症候群・広汎性発達障害・自閉症というワードが出てくるかと思いますが、これらもすべてASDに含まれます。
ASDの原因は、現時点で詳しく解明されていませんが、生まれつきの脳の機能に原因があると言われています。
近年では20から50人に1人が自閉症スペクトラムと言われており、男性が割合的に多いと言われています。
具体的な症状は
●視線が合わない
●表情が乏しい
●偏食
●名前を呼んでも振り向かない
●パニック・睡眠障害
などがあります。
基本的に投薬などの治療はなく、本人の特徴・性質に合わせた療育・教育が主な対処方法になっています。
ただ、パニックや睡眠障害など本人の健康に弊害が出る場合は投薬を用いられる事があります。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)
ADHDは、不注意・多動・衝動的が目立つ発達障害で、子供の20人に1人は存在していると言われています。「際立って手がかかる子」「手が付けられないくらい暴れる子」 と思われがちですが、けっして親のしつけ等が原因ではなく、行動・感情をコントロールする前頭葉の機能に原因があると言われています。
ADHDの種類は3つに分類されており
●不注意型(集中力不足・忘れ物が多い・他からの刺激ですぐに気を取られるなど)
●衝動・多動型(落ち着かない・感情のコントロールが苦手)
●混合型(不注意型・衝動多動型の両方を兼ねている)
があります。
ADHDは大人になると症状が落ち着いていくパターンもありますが、近年では「大人の発達障害(ADHD)」が話題になっており、大人になっても症状が続くパターンや、アルコールや薬物依存などを併発してしまうパターンもあります。
対処法は、本人の特性に合わせた環境調整(忘れ物等の対処はメモやチェックリストを活用する・本人の特性に付いて周囲に伝えておくなど)や、症状によっては投薬治療なども行われています。
学習障害(LD)
LDは知的や発達面は正常なものの学習面のみで起こる障害です。それゆえ、本格的な学習生活に入る小学校に上がってから発覚するパターンも多く 原因は脳機能の障害と言われていますが、はっきりとは分かっていません。
LDの傾向は3つに分かれており
●読字障害・ディスレクシア(字の読み間違い・文字や文章が理解できない)
●書字表出障害・ディスグラシア(文字が正しく書けない・書き写しや文の作成に時間がかかる)
●算数障害ディスカリキュア(数の概念を理解しづらい・計算が困難)
があります。
これらの症状から「勉強が出来ない人」と捉えられがちですが、けして本人の努力不足などではありません。
対処法としては、字が拡大された教材を使用する・PCやスマホなど電子機器の読み上げ機能を使用する、イラストを使用して数の概念を理解させる、など学習方法や教材の工夫、周囲の理解が必要不可欠になります。
2. 発達障害の「グレーゾーン」とは

グレーゾーンは簡潔に言えば
その特性や症状はいくつか持っているものの、ハッキリ診断する基準に達しない
状況を言います。
発達グレーゾーンは、発達障害の診断がつく程度ではないものの、障害特有の症状や傾向は持っているという、「狭間にある」状況ともいえますが
ハッキリ診断されている子どもと比べると、出来る事がたくさんあるとも言えます。
発達障害と違って、グレーゾーンの子どもは診断も無ければ手帳の給付もありませんが、療育や発達支援を受ける事ができます。
未就学児の場合は、グレーゾーンの方のためのサークルも、地域で行われている場合もあります。
3. 軽症者の人とのコミュニケーションで気をつけることとは
軽度の発達障害の場合やグレーゾーンの場合でも
普段の生活の中で病状・特性にしっかりと理解を持ちつつ、コミュニケーションを工夫して行わなければなりません。
とくに気をつけるべき事は何なのでしょうか?

例を言えば「今日学校どうだった?」という話しをしたい時は「今日は学校で何をしたの?」「学校遅れるよ」と朝の準備を急ぐように伝えたい時は「8時になったら着替えましょう」など、より明確に伝える事です。
含みのある言い方や、その気持ちにさせたい言い方をするのではなく、ストレートに分かりやすく伝えましょう。
「学校から帰ったら手を洗って、着替えて、宿題を終わらせてね。」
という言い方だと、本人を混乱させてしまう場合があります。
一度に幾つもの事柄を伝えるのではなく、「手を洗って」それが終われば「着替えてね」それが終われば「宿題を終わらせてね」と1つ1つタイムリーに伝えてあげるとすんなり受け入れてくれる場合もあります。
お子様の特性によっては「やる事リスト」を紙であらわして、明確に示してあげる事も一案です。
発達障害を持った子どもは、できない事を気にして自信を喪失していたり 偏りある特性ゆえ、周囲に距離を置かれ、原因が分からずストレスを抱えてしまったり 生きづらさを感じながら普段の生活を頑張っている場合があります。
身近にいる大人ができることはまず、本人の得意・不得意を見つけ、両方を理解してあげる事です。
得意な事を伸ばし、不得意な事を理解し適切な対処をする事は、子どもにあった教育と環境を提供することに繋がります。
とくに気をつけるべき事は何なのでしょうか?

指示やお願いは具体的に
まず抽象的な言い方は避け、具体的に何をしてほしいかを的確な情報を伝える事が肝心です。例を言えば「今日学校どうだった?」という話しをしたい時は「今日は学校で何をしたの?」「学校遅れるよ」と朝の準備を急ぐように伝えたい時は「8時になったら着替えましょう」など、より明確に伝える事です。
含みのある言い方や、その気持ちにさせたい言い方をするのではなく、ストレートに分かりやすく伝えましょう。
簡潔に、ひとつずつ伝える
簡潔に伝えるのも、本人に伝わりやすくするコツです。「学校から帰ったら手を洗って、着替えて、宿題を終わらせてね。」
という言い方だと、本人を混乱させてしまう場合があります。
一度に幾つもの事柄を伝えるのではなく、「手を洗って」それが終われば「着替えてね」それが終われば「宿題を終わらせてね」と1つ1つタイムリーに伝えてあげるとすんなり受け入れてくれる場合もあります。
お子様の特性によっては「やる事リスト」を紙であらわして、明確に示してあげる事も一案です。
本人の得意・不得意を理解してあげる
得意・不得意に偏りがあるのも、発達障害の特徴です。発達障害を持った子どもは、できない事を気にして自信を喪失していたり 偏りある特性ゆえ、周囲に距離を置かれ、原因が分からずストレスを抱えてしまったり 生きづらさを感じながら普段の生活を頑張っている場合があります。
身近にいる大人ができることはまず、本人の得意・不得意を見つけ、両方を理解してあげる事です。
得意な事を伸ばし、不得意な事を理解し適切な対処をする事は、子どもにあった教育と環境を提供することに繋がります。
4. まとめ

以上、子どもの発達障害・種類や特性の違い・グレーゾーンの概要や適した話し方などをお伝えしてきました。
まとめると以下になります!
●発達障害は、ASD(自閉スペクトラム)・ADHD(多動性・衝動性)・LD(学習障害)の種類がある
●グレーゾーンとは、特性を持っているが、診断が下るまでの状況ではない状況の事
●発達障害の為への対処法は、具体的に伝える・タイムリーに簡潔に伝える・得意不得意を理解するなど
という事でした!
発達障害という言葉を聞いてしまうと、調べれば調べるほど、何の対処から行えば良いか悩んでしまいますよね。
まずは、発達障害が何か・親が子どもの持つ特性をしっかりと理解し、時には相談先・専門家の手を借りる事が適切な対処に繋がるかと思います。
これらの情報が参考になれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
