
子供は発達障害なのかな?グレーゾーンの子への親の対応方法は?
「落ち着きがない」
「怒りだすと止まらない」
「気持ちの切り替えが苦手そう」
子どもの行動や言動が気になり、ネットで「発達障害」と検索したことがある人もいるのではないでしょうか?
子どもへの対応が難しいと感じているママは少なくありません。
保育園や幼稚園での集団生活は普通に送れているので、あまり気にしたことがなかったけれど、ふと子どもの行動や言動が気になるときがあります。
この記事では「発達障害かも?」と思ったときにどこに相談すればいいのか、親として子どもにどのように接すればいいのかについて解説します。
子どもの発達で気になることがあっても、周りに相談せず1人で悩んでいるママは多いです。
発達に凸凹がある子どもは、その子に合った環境を作ってあげることで症状が改善していきます。
この記事を読んで一度誰かに相談してみることをおすすめします。
1. 発達障害の「グレーゾーン」とは
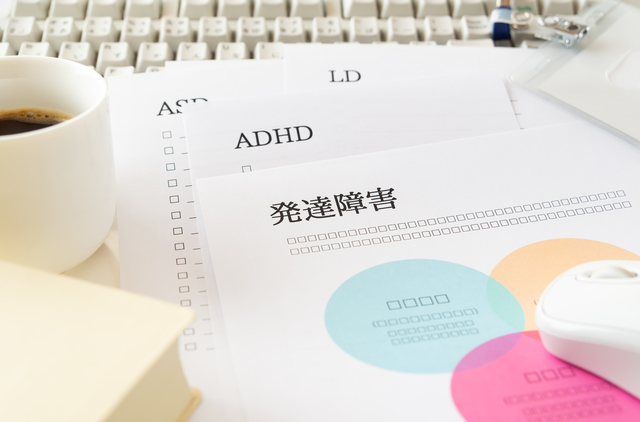
発達障害の「グレーゾーン」とは、発達障害の確定診断が出ていない状態のことを言います。
発達障害には以下のようなものがあります。
| 名称 | 特徴 |
| ASD(自閉症スペクトラム症) | ・空気を読みにくい ・人の気持ちを読み取りづらい ・コミュニケーション力が低い ・こだわりが強い など |
| ADHD(注意欠陥・多動症) | ・忘れ物が多い ・ソワソワする ・衝動を抑えられない など |
| LD(学習障害) | 知的能力に問題はないが、特定の科目だけができない など |
これらの特性は合併することが多く、「自閉症スペクトラム症」と診断されても「注意欠陥・多動症」の特性も一緒に見られることがよくあるのです。
「グレーゾーン」の子どもはこれらの症状が見られるものの、基準をすべて満たしていないため発達障害と診断されません。
診断が出ていないからと言って、その症状が軽度だったり、生活に支障がないというわけではないのです。
グレーゾーンの子どもは周りから誤解されやすく、悩んでいる親御さんが多くいます。
2. 「発達障害かも?」と思ったら

生活の中で子どもの行動や言動を見て「発達障害かも?」と思うことがあるでしょう。
そんなときにどこに、誰に相談すればいいのか悩む人は多いです。
相談先は以下のようなところがあります。
・保育園や幼稚園、学校
・自治体の支援センター
・小児科や児童精神科 など
子どもの発達障害は、できるだけ早く相談し子どもに合った環境を作ってあげることで症状を落ち着かせることができます。
1人で抱え込まずに、まずは相談してみることが大切です。
ここでは、それぞれの相談先について詳しく解説します。
2-1. 保育園や幼稚園の先生に相談する
保育園や幼稚園に通っているのであれば、先生に園での様子を聞いたり、気になることを相談したりしてみましょう。
園の先生は保育の専門家であるため、さまざまな視点から子どもの様子や今後の対応方法について教えてくれます。
子どもに合った環境を整える意味でも、保育園や幼稚園の先生たちとの連携は必要不可欠です。
また、家の外での様子はどうなのか先生に聞いてみると気づくことがあるかもしれません。
グレーゾーンの子どもの中には、保育園や幼稚園では特に問題を起こすことなく普通に過ごしているが、家では暴言を吐いたり、暴力をふるってしまったりするという子もいます。
どのような状況で特性が出てしまうのかを分析することで、子どもの問題行動が起きにくくなる可能性もあるのです。
園の先生たちは、保育のプロとしてアドバイスをくれるので安心して相談してみましょう。
2-2. 自治体の支援センターで相談する
各自治体には、子育て中の悩みや発達に関する相談ができる窓口がさまざまあります。
例えば、以下のようなところです。
・保健センター
・子育て支援センター
・児童相談所
・療育センター など
自治体によって呼び方が違っていますが、このようなセンターで相談するのも一つの方法です。
それぞれのセンターには、保健師やカウンセラー、保育士など子育てに関する専門家がいるので相談しやすいでしょう。
「グレーゾーン」であっても、子どもの特性や状況によっては療育サービスを受けられたり、支援を受けられたりすることもあります。
1歳半検診や3歳検診など定期検診で相談してみるのも良いでしょう。
2-3. 病院に相談する
発達で気になることがあれば、病院に相談するのもいいでしょう。
まずはかかりつけの小児科で相談し、状況に応じて発達の検査を受けるための病院を紹介してくれます。
予防接種や定期検診の際に、気になることがあれば遠慮なく相談してみましょう。
3. 親はどう対応したらよい?

子どもの行動や言動が気になると、どのように接すればいいのか悩む人は多いです。
突然叫び出したり、乱暴になったりするとついつい怒りたくなってしまいますよね。
親の対応としては以下のことを心がけましょう。
・決して治そうとしないこと
・日常を観察して刺激を減らしてあげる
・親以外の協力者を作っておくこと
子どもの特性を親だけで抱えるのではなく、親以外の協力者を作ることはとても大切です。
ここから、詳しく解説します。
3-1. 決して治そうとしないこと
発達の特性は、急に治るものではありません。
言うことを聞かなかったり、できないことがあったりすることにイライラしてしまう気持ちもよくわかります。
ですが、その特性も子どもの個性だと捉えて否定せず温かく子どもの成長を見守りましょう。
こういった特性を持っている子どもは、家の外だと誤解されやすく生きづらさを感じることがあります。
子どもの心が折れてしまわないようにするためには、家でお母さんやお父さんが優しく見守り安心できる場所があることが大切です。
3-2. 日常を観察して刺激を減らしてあげる
子どもがどのように過ごしているのか注意深く観察してみましょう。
そうすると、どういうときに特性が出るのかがわかってきます。
発達の凹凸を少なくしていくためには、その子にとってどのようなことが刺激になっているのかを理解することが大事です。
刺激には以下のようなものがあります。
・大きな音
・いろんな人の話し声
・いつもとは違う生活リズム など
何が子どもにとっての刺激になっていて、特性が出ているのかは人によってさまざまです。
子どもに合った環境を整えるためにも、刺激になることを減らしてあげましょう。
3-3. 親以外の協力者を作っておくこと
発達障害の特性があると「親がなんとかしなければいけない」と考える人も多くいます。
そんなに頑張らなくても大丈夫です。
園やサービスなどを活用して親以外に協力してくれる人を作っておきましょう。
なぜなら、子どもが自立できるような環境を作っておくことが大事だからです。
発達障害の特性を持っている子どもは、なかなか人を信頼できず関係構築までに時間がかかります。
療育サービスや園の先生などと協力をしながら、子どもが安心して過ごせる、素を出せる場所を作ってあげましょう。
特性を持っている子でもいつかは自立していかなければなりません。
心配で子どもを囲い込みたくなる気持ちもわかりますが、子どもの自立を考えれば親以外に信頼できる人を作っておくのは重要です。
4. まとめ

この記事では、「グレーゾーン」とは何かということから、「発達障害かも?」と思ったときの相談先、親としての対応について解説しました。
「子どもが発達障害かもしれない」と思っている親御さんは少なくありません。
気になることがあれば、保育園や幼稚園の先生、自治体の支援センター、病院などに相談してみましょう。
発達の凹凸を改善していくためには、できるだけ早くその子に合った環境に置いてあげることが大切です。
あなたが今気になっているのであれば、一度相談してみるといいでしょう。
発達障害の特性は簡単に治るものではありません。
それも子どもの個性と捉えて、伸ばせるところは伸ばして、刺激になるものはなるべく取り除いてあげるのも一つの方法です。
親が1人で抱え込むのではなく、周りの人たちと協力しながら子どもの成長を見守っていきましょう。
