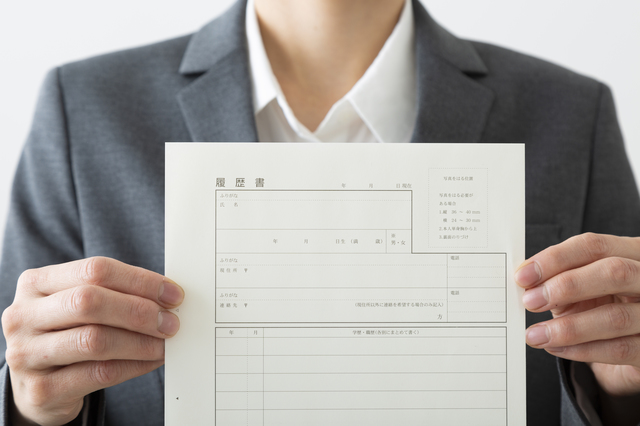
転職におすすめでアラサーからでもスキルアップに繋がる資格は?またその資格内容や取得難易度について!
公開日: 2022/3/4
転職する時に資格を持っていると有利になると思い資格取得を考えていても、実際にどの資格を取得すれば良いのかはっきりと分からない方が多いです。
さらに、せっかく努力して資格を取得しても、それがスキルアップに繋がらなければほとんど意味がありません。
また、転職したい会社の業種によっても求められるスキルや資格は大きく変わり一概に有利な資格はありませんし、アラサーになると無駄な時間はできるだけ避けたいと思います。
そこで今回は、これから転職に向けて資格取得を考えている方に向けて、おすすめの資格について詳しく紹介します。
さらに、せっかく努力して資格を取得しても、それがスキルアップに繋がらなければほとんど意味がありません。
また、転職したい会社の業種によっても求められるスキルや資格は大きく変わり一概に有利な資格はありませんし、アラサーになると無駄な時間はできるだけ避けたいと思います。
そこで今回は、これから転職に向けて資格取得を考えている方に向けて、おすすめの資格について詳しく紹介します。
1. メンタルヘルス・マネジメント検定とは

そのため、メンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を身に付けることができます。
まず最初に、そんなメンタルヘルス・マネジメント検定について3つ紹介します。
1-1. 立場や目的に合わせた3つのコースがある
この資格には以下の3つのコースがあり、それぞれ役割が異なります。
・「Ⅰ種マスターコース」
人事部や経営幹部に社内のメンタルヘルス対策を推進する
・「Ⅱ種ラインケアコース」
管理所に対して部下へのメンタルヘルス対策を推進する
・「Ⅲ種セルフケアコース」
一般社員に対して組織における社員自らのメンタルヘルス対策を推進する
試験では、基本的に選択問題を行いますが、Ⅰ種マスターコースでは選択問題に加え論述問題も出題されるので少し難易度が高くなっています。
そのため、1種マスターコースを考えている方は注意が必要です。
・「Ⅰ種マスターコース」
人事部や経営幹部に社内のメンタルヘルス対策を推進する
・「Ⅱ種ラインケアコース」
管理所に対して部下へのメンタルヘルス対策を推進する
・「Ⅲ種セルフケアコース」
一般社員に対して組織における社員自らのメンタルヘルス対策を推進する
試験では、基本的に選択問題を行いますが、Ⅰ種マスターコースでは選択問題に加え論述問題も出題されるので少し難易度が高くなっています。
そのため、1種マスターコースを考えている方は注意が必要です。
1-2. メンタルヘルス・マネジメント検定の難易度はどれくらい?
Ⅱ種ラインケアコースでは、合格率40%以上ありⅢ種セルフケアコースでは、合格率60%以上と半数近くまたは半数以上が合格できる難易度です。
しかし、Ⅰ種マスターコースでは、先ほども説明してように選択問題に加え論述問題も出題されるので、合格率は20%以下ととても低くなっています。
そのため、Ⅱ種ラインケアコースとⅢ種セルフケアコースは比較的にしっかりと勉強すれば合格できる可能性が高いですが、Ⅰ種マスターコースの難易度は高いと言えます。
しかし、Ⅰ種マスターコースでは、先ほども説明してように選択問題に加え論述問題も出題されるので、合格率は20%以下ととても低くなっています。
そのため、Ⅱ種ラインケアコースとⅢ種セルフケアコースは比較的にしっかりと勉強すれば合格できる可能性が高いですが、Ⅰ種マスターコースの難易度は高いと言えます。
1-3. 転職時に役立つ資格ではないが、活かせる職種は多岐にわたる
具体的に実用性のある業種などはありませんが、企業での従業員のメンタルヘルス不調などのサポートや生産性を上げるためのサポートなどに生かすことが可能です。
そのため、特定の業種に限らず幅広い業界で生かすことができる資格になります。
そのため、特定の業種に限らず幅広い業界で生かすことができる資格になります。
2. ビジネスマネジャー検定とは

続いては、そんなビジネスマネジャー検定について3つ紹介します。
2-1. 職場における様々な「マネジメント」について網羅的に学ぶ
組織で活動する場合に求められるマネジメント力やリーダー性など多くの職場で求めれるマネージャーの基礎知識やスキルを学ぶことができます。
さらに、特定の業種に限らず多くの業種で活用することができるスキルなので、応用的なとても便利な知識です。
さらに、特定の業種に限らず多くの業種で活用することができるスキルなので、応用的なとても便利な知識です。
2-2. ビジネスマネジャー検定の難易度はどれくらい?
ビジネスマネジャー検定では、100点満点中70点以上の点数を獲得することができれば合格することができます。
また、2015年にできて以降、毎年の合格率は平均約50%前後でしっかり勉強すれば合格することができる資格になります。
しかし、今後試験内容が見直され難易度が高まっていく可能性も考えられるので、その可能性も視野に入れておくことが大切です。
また、2015年にできて以降、毎年の合格率は平均約50%前後でしっかり勉強すれば合格することができる資格になります。
しかし、今後試験内容が見直され難易度が高まっていく可能性も考えられるので、その可能性も視野に入れておくことが大切です。
2-3. 管理職への転職を目指す場合は有利になることも
管理職の立場上、この資格で得られるスキルや基礎知識がとても重要になります。
管理職は、多くのメンバーと円滑にコミュニケーションを行ったり部下のマネジメントや団結力などが必要です。
そのため、管理職への昇進を目指している方や、管理職に転職したいと考えている方はビジネスマネジャー検定の取得でとても有利になる場合があります。
管理職は、多くのメンバーと円滑にコミュニケーションを行ったり部下のマネジメントや団結力などが必要です。
そのため、管理職への昇進を目指している方や、管理職に転職したいと考えている方はビジネスマネジャー検定の取得でとても有利になる場合があります。
3. ビジネス実務法務検定とは
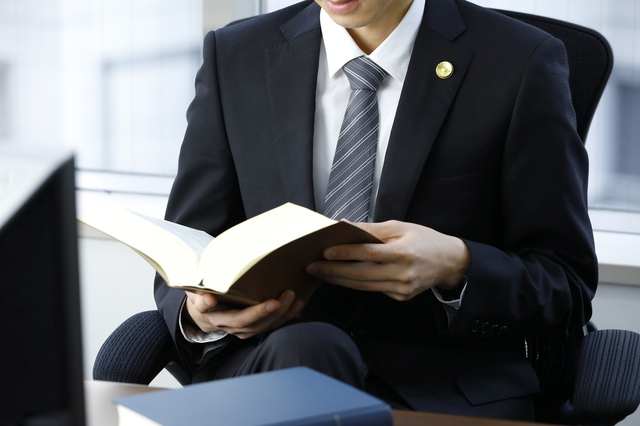
特に契約書の契約内容をしっかり把握し不備や不利益がないかしっかりと判断できる能力が身につきます。
続いては、そんなビジネス実務法務検定について3つ紹介します。
3-1. 3級から1級まであり、級が上がるにつれてより専門的になる
ビジネス実務法務検定の3級では、契約についての知識や企業と会社の仕組みなど基本的なビジネスの法務に関する問題が出題されます。
しかし、級が上がるにつれ、法律に関する深い理解度や実務に支障をきたさないような応用レベルのスキル、損害賠償や債権管理などの幅広い知識が求められます。
そして1級では、あらゆるビジネスに通用する法律実務知識があり、高度な判断能力や対応力が求められるようになります。
しかし、級が上がるにつれ、法律に関する深い理解度や実務に支障をきたさないような応用レベルのスキル、損害賠償や債権管理などの幅広い知識が求められます。
そして1級では、あらゆるビジネスに通用する法律実務知識があり、高度な判断能力や対応力が求められるようになります。
3-2. ビジネス実務法務検定の難易度はどれくらい?
ビジネス実務法務検定の3級では合格率が平均で約60〜70%あり、しっかり勉強していれば合格することもできます。
しかし、2級になると合格率は約40%になり半分以上の方が不合格になってしまうほどの難易度になります。
そして、もっとも専門的なスキルや知識を求められる1級では、合格率が10%前後にまで低くなります。
そのため、かなり勉強して試験に挑戦しても合格できる可能性とても低いので、いきなり受けることはおすすめしません。
しかし、2級になると合格率は約40%になり半分以上の方が不合格になってしまうほどの難易度になります。
そして、もっとも専門的なスキルや知識を求められる1級では、合格率が10%前後にまで低くなります。
そのため、かなり勉強して試験に挑戦しても合格できる可能性とても低いので、いきなり受けることはおすすめしません。
3-3. 2級以上を取得すると転職時に評価されやすい
ビジネス実務法務検定の2級以上を取得していると、転職時に評価されやすくなり転職活動が有利に働くことが多くなります。
2級であってもある程度専門的な知識やスキルを持っていないと合格することができないため、多くの方にとってわかりずらいもしくはわからない知識やスキルを組織に共有することができ、とても重宝されます。
さらに、多くの企業との取引や契約、損害賠償や債務管理など難しい分野でもしっかり対応する力が身についているので、幅広い分野で活躍することができます。
また、1級を取得している場合では、その資格を持っている方がほとんどいないため、高確率で転職時に評価されることでしょう。
2級であってもある程度専門的な知識やスキルを持っていないと合格することができないため、多くの方にとってわかりずらいもしくはわからない知識やスキルを組織に共有することができ、とても重宝されます。
さらに、多くの企業との取引や契約、損害賠償や債務管理など難しい分野でもしっかり対応する力が身についているので、幅広い分野で活躍することができます。
また、1級を取得している場合では、その資格を持っている方がほとんどいないため、高確率で転職時に評価されることでしょう。
4. まとめ

しかし、実際にどの資格を取得していれば転職活動で有利に働かせることができるのかわからない方も多いです。
今回紹介した資格は、幅広い分野で応用的に生かすことができ、面接でも評価されやすい資格です。
そのため、これから転職のためのスキルアップで資格取得を考えている方は、ぜひ今回の記事を参考してみてください。
