
個人事業主にとってのインボイス制度とは?登録しなかった場合のデメリットも解説
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度。
多くの人たちに影響を及ぼし、インターネットでもさまざまな解説サイトが増加しています。
そのなかでも戸惑いの声が大きいのが個人事業主です。
何をどうすれば良いのかわからない、罰則はあるのかなどの声が高まっています。
本記事では、個人事業主にとっての陰ボス制度について解説します。
登録しなかった場合のデメリットについても紹介するので、参考にしてください。
1. インボイス制度について

個人事業主にとってのインボイス制度を説明するうえで欠かせないのが、インボイス制度の仕組みや内容についての理解です。
そもそも、インボイス制度とはどのような制度で、どんな手続きが必要なのでしょう。
ここでは、インボイス制度そのものについて解説するので、参考にしてください。
1-1. 適格請求書
インボイス制度とは、簡単にいえば適格請求書を用いた取引制度のことです。
適格請求書とは、以下の6つの項目が記載された請求書を指します。
・適格請求書発行事業者の名称(氏名)と登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分された対価の合計金額(税込税抜どちらでも可)と、適用税率
・税率ごとに区分された消費税額
・適格請求書の交付を受ける事業やの名称(氏名)
上記のこれら6つすべての項目が記載されたもののみが、適格請求書です。
それ以外の請求書は適格請求書としての役目を果たさないので注意してください。
1-2. 事業者登録の申請
適格請求書の発行には、事業者登録が必要です。
これまで多くの個人事業主は、独自の請求書のひな型を作成して発行していたでしょう。
また、取引先から独自の請求書のひな型が送られてきて、そこに必要事項を書いて提出するケースもあったかもしれません。
しかし、適格請求書には前項目で紹介したように6項目の記載が必要です。
このなかで特に重要となるのが登録番号であり、この番号は登録申請しなければ発行されません。
登録申請については国税庁のホームページをご覧ください。
申請に必要な書類がダウンロードでき、相談窓口の電話番号なども記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
1-3. 申請期限は原則2023年9月30日
適格請求書発行事業登録の申請期限は、原則2023年9月30日まででした。
その理由は、2023年10月1日からインボイス制度が施行されるからです。
施行と同時に適格請求書を発行するためには、それまでに申請を行って登録番号を発行してもらわなければいけません。
そのため、施行される前日の2023年9月30日までの登録が必要でした。
ただし、登録をしなかったからといって何らかの罰則が科せられるわけではありません。
2023年10月1日以降も登録申請をしていない個人事業主は、存在します。
1-4. 目安は課税売上1,000万円
なお、インボイス制度の対象は全事業者ではありません。
目安は年間の課税売上1,000万円以上で、それ以下の場合は原則対象外です。
簡単に言い換えると年間の課税売上額が1,000万円を超えている場合は、インボイス制度の対象となるため、事業者登録を行って適格請求書を発行しなければいけません。
一方、1,000万円を超えない場合はインボイス制度の対象外となり、事業者登録の申請も適格請求書の発行もしなくて良いのです。
2. 個人事業主とインボイス制度

インボイス制度そのものについて解説してきました。
制度の内容がある程度理解できたところで、それでは個人事業主にとってのインボイス制度とはどのようなものなのでしょう。
主な注目ポイントは以下の3つです。
・義務ではない
・取引先と要相談
・6年間の経過措置期間あり
それぞれの注目ポイントについて解説するので、参考にしてください。
2-1. 義務ではない
個人事業主の場合、インボイス制度の対応は義務ではありません。
その理由は、年間の課税売上額が1,000万円に満たない可能性が高いからです。
年間の課税売上額1,000万円という金額は、法人化するかしないかのラインでもあります。
このラインを超えた場合、法人化したほうが納める税金が安くなるため、法人化するケースが多いでしょう。
個人事業主であっても1,000万円を超えると納税額が一気に高くなるため、法人化を選択する人が多いのが現状です。
個人事業主のままで事業を継続していく場合は、納税額の観点から1,000万円を超えていないケースが多いと予想されるため、インボイス制度の対象から外れます。
そのため、多くの個人事業主の場合は義務ではなくなるのです。
2-2. 取引先と要相談
多くの個人事業主の場合は、取引先との相談が必要になるでしょう。
取引先によって、インボイス制度への対応の仕方が異なるからです。
考えられるケースとしては以下の3パターンがあげられます。
・適格請求書発行事業者への登録申請
・年間課税売上額が1,000万円を越えなければ対応不要
・対応不要
どのパターンを迫られるかは取引先によって異なるので確認が必要です。
どのように対応すれば良いのか、確認してください。
2-3. 6年間の経過措置期間あり
なお、個人事業主として適格請求書発行事業者に登録した場合は、6年間の経過措置期間が適用されます。
控除期間とその内容は以下の通りです。
・2023年10月1日~2023年9月30日:課税仕入れの80%が控除
・2026年10月1日~2029年9月30日:課税仕入れの50%が控除
なお、これらの控除には帳簿と請求書のそれぞれに具体的な要件が設けられており、満たしていなければ対象にはなりません。
帳簿と請求書のそれぞれの要件については、国税庁のホームページを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
3. 登録しなかった場合の個人事業主のデメリット
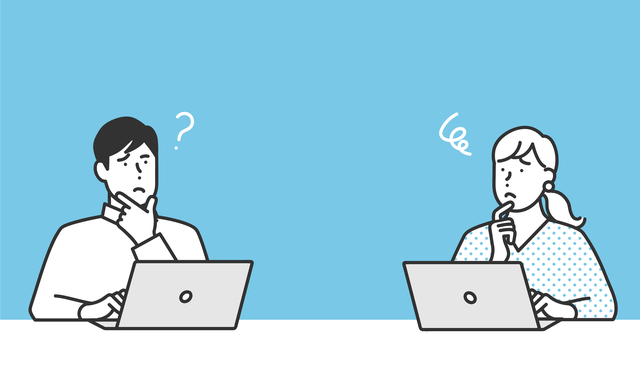
個人事業主については年間の課税売上額の観点から、インボイス制度の対応は義務ではありません。
しかしその一方で、登録しなかった場合には以下のようなデメリットが考えられます。
・契約打ち切りの可能性あり
・報酬減額の可能性あり
・新規契約が断られる可能性あり
それぞれのデメリットについて解説するので、参考にしてください。
3-1. 契約を打ち切られる可能性がある
個人事業主が登録しなかった場合、これまでの取引先から契約が打ち切られる可能性があります。
その理由は、取引先の売上が激減するからです。
例えば、個人事業主と取引先との間で1か月50万円(税込)の契約を結んでいたとしましょう。
取引先は報酬として毎月個人事業主に50万円を支払います。
このとき、個人事業主が適格請求書発行事業者に登録していれば50万円のうちの10%にあたる5万円を消費税として国に納めます。
一方の取引先は個人事業主が消費税を支払っているため、5万円を納税する必要はありません。
しかし、個人事業主が適格請求書発行事業者に登録していなかった場合は免税対象となるため、5万円を納税する必要はなくなります。
その代わり、取引先が個人事業主に代わって消費税分の5万円を納税しなければいけません。
このように取引先にとっては5万円を別に納税しなければならなくなり、売上が減少してしまいます。
その理由から契約が打ち切られる可能性があるので、注意してください。
3-2. 報酬が下げられる可能性がある
報酬が下げられる可能性もあるでしょう。
その理由は、契約が打ち切られるパターンと同様です。
取引先は、個人事業主の代わりに消費税の納税をしなければなりません。
その分をマイナスした金額を契約料として支払うという申し出がされるでしょう。
個人事業主としては、毎月50万円の収入が45万円に減額されることになるのです。
3-3. 新規契約が結びにくくなる可能性がある
新規契約が結びにくくなる可能性も考えられます。
理由は契約が内気になる可能性と同様です。
取引先としては、売上が減少することは避けたいと考えます。
また、インボイス制度の手続きは時間と手間がかかるため、相手がきちんと消費税を納税してくれたほうが良いのです。
適格請求書発行事業者に登録していない個人事業主の場合は、売上が減少するうえに事務作業の手続きが煩雑になってしまいます。
メリットがあまりないと考えれば、新規契約を結ぼうとは思わないでしょう。
4. 取引先と相談したうえでよく考えよう
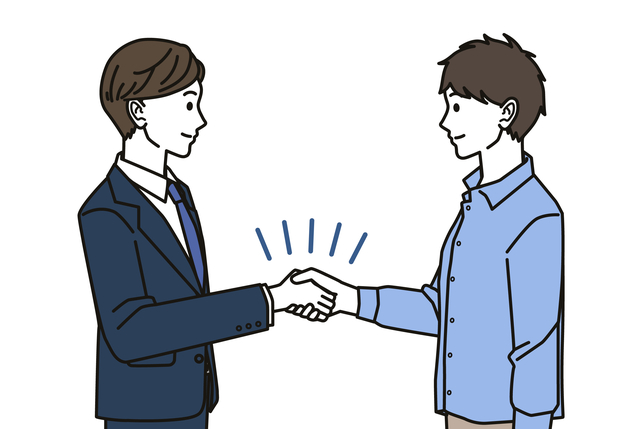
個人事業主にとってのインボイス制度について解説しました。
年間の課税売上額の観点から見れば、個人事業主のインボイス制度登録は義務ではありません。
しかしその一方で取引先の観点からすると、登録して欲しいと思うところも出てくるでしょう。
どのような対応が迫られるのかは、取引先と相談したほうが良いといえます。
現在の取引先はもちろん、新たに新規契約を結ぶ際にも必ず確認してください。
